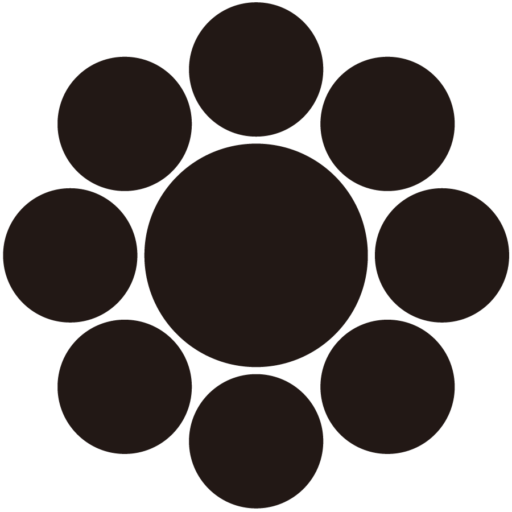
「京都」の地と細川家の関係性

細川家といえば九州は「熊本」発祥の名家であるということは知られておりますが、実は京都の「地」とも深く兼ね合いがあることでも知られております。
細川家の興り
細川家には「嫡流」と、「傍流」とがあります。
そもそも「嫡流」とは氏族の正統な本家を指し、嫡系や本家とも呼ばれます。一方の「傍流」は本家から分かれた家筋や血統を意味します。
細川家はもともと、細川義季を初祖とし、室町時代に畿内・四国を中心に活躍した一門で8か国の守護職を占める有力大名です。
その細川義季を初め、細川京兆家(ほそかわけいちょうけ)が嫡流であり、義季から、満元-持之-勝元-政元に至っては、代々幕府管領役として幕政の中枢として活躍しました。
ちなみに「京兆」とは右京大夫の唐名「京兆尹」のことであり、当主が代々右京大夫の官位に任ぜられたことに由来します。
しかし嫡流はその後戦国時代の内紛により、流れが途絶えてしまいます。
一方、佐々木源氏をルーツに持つ細川藤孝(幽斎)を祖とする傍流が、織田氏・豊臣氏・徳川氏に仕えて次々に出世し、江戸時代には肥後熊本藩54万石の藩主家となり、明治維新後には華族の侯爵家に列しました。
こちらの「傍流」が、群雄割拠な戦国時代から始まり、現代に至るまでの細川家の華麗なる歴史を築いていったのです。
京都と細川家の兼ね合い
そんな細川家ですが、京都の地とゆかりが深い家系でもあることで知られております。
長岡京市の勝龍寺城
細川藤孝が織田信長のもとで頭角をあらわし、細川家繁栄の基礎を築いたのが、現在京都にある長岡京市の勝龍寺城(青龍寺城)を居城としていた時期です。
細川家の菩提寺
また元々細川家の菩提寺は京都・建仁寺の塔頭永源庵(現在の正伝永源院)であり、同じく現在の京都市北区にある大徳寺高桐院は細川忠興が父・藤孝の菩提寺として創建したお寺でもあります。
現在でもこちらに細川藤孝は祀られており、当の忠興に至っても、遺言によりその「遺歯」が高桐院に埋葬されたと言います。
細川ガラシャ隠棲の地「味土野」
また京丹後市弥栄町味土野は、細川ガラシャが本能寺の変の後、逆臣の娘となったために細川忠興によって「幽閉された地」として伝わる場所です。
ここ味土野は、標高613メートルの修験の山、金剛童子山の山裾の秘境にあり、絶好の隠れ家でした。
今はそこに屋敷跡が残っていますが、その跡から当時は城というより粗末な砦のような建物だったのではないかと推測されております。
旧細川家別邸
現在、京都府左京区にある旧細川家別邸(ほそかわけべってい)は、京都市名勝庭園に指定されております。
こちらは元々、細川家第16代細川護立によって昭和11年(1936年)に建てられた、昭和初期の代表的華族邸宅(旧細川侯爵邸)です。
また17代当主であり、内閣総理大臣としても活躍した細川護貞が、当時京都大学に通う際、下宿地として利用していた地でも知られております。

アイキャッチ-2.jpg)
アイキャッチ.jpg)
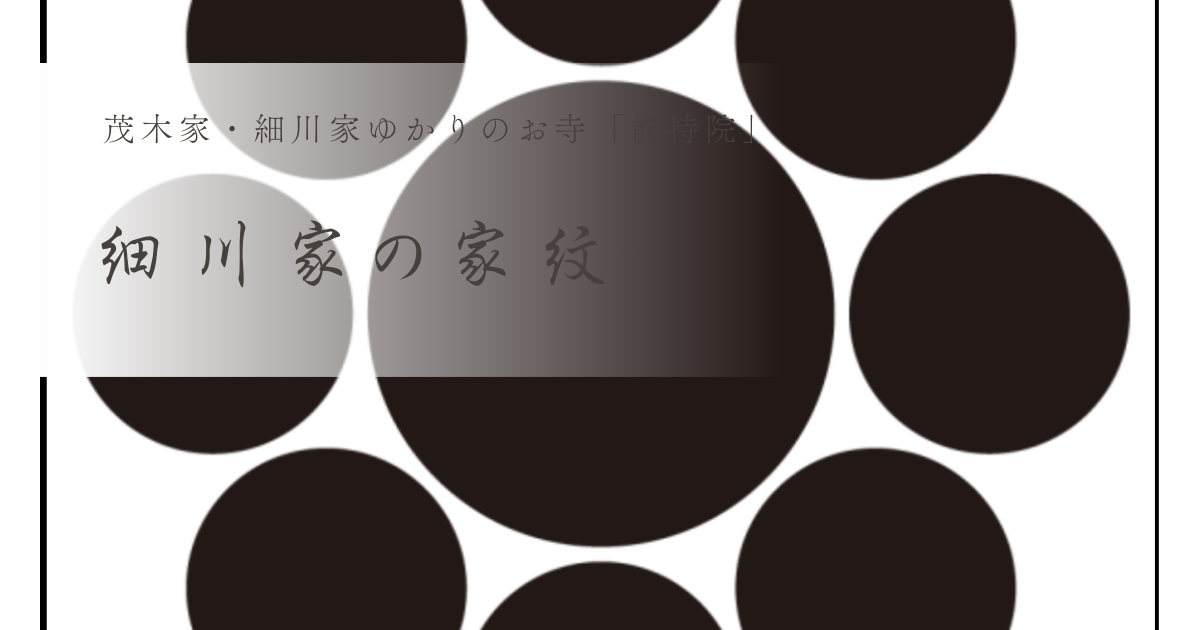
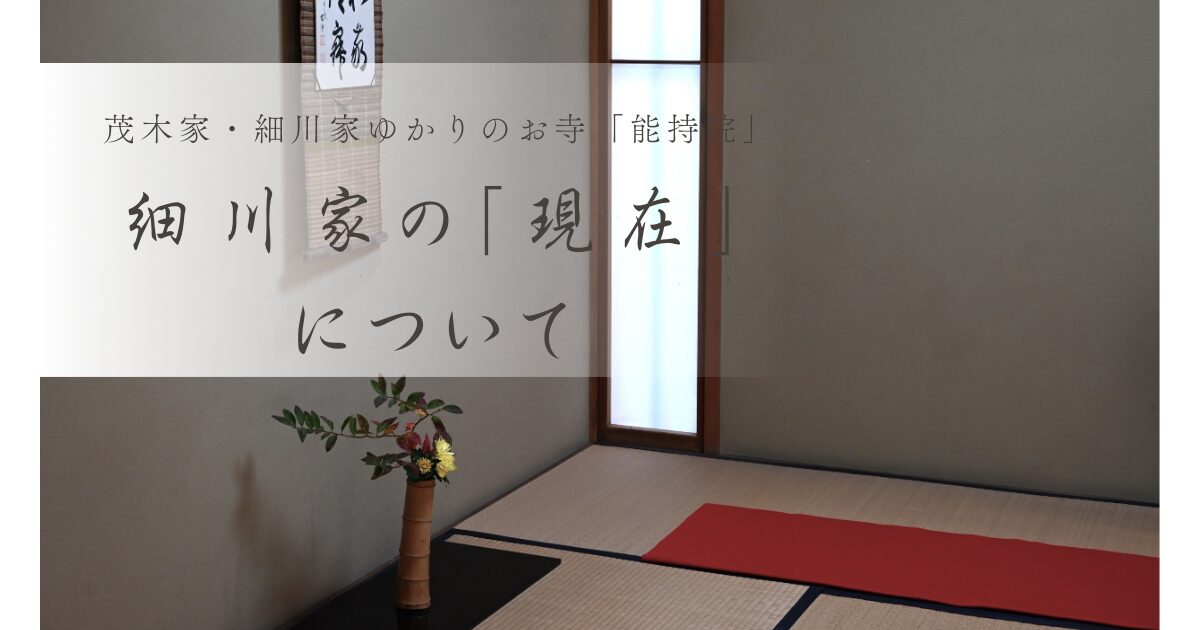
この記事へのコメントはありません。