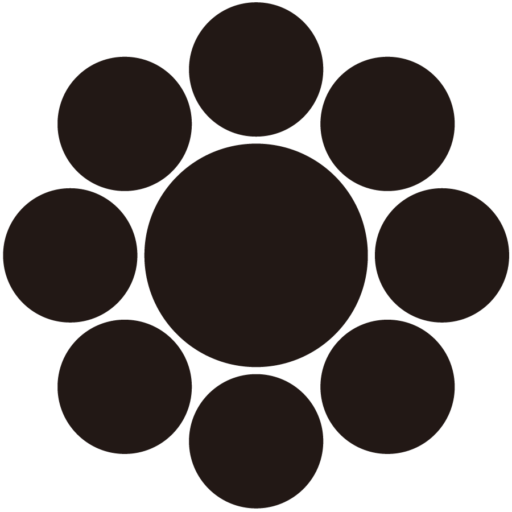
本堂
木造平屋銅板葺向拝玄関唐破風造、桁行六十尺余梁間四十九尺余八間七面の建物です。
本堂にお祀りされているのは「十一面観世音菩薩」です。
十一面の顔を持つ観音様で、この十一面は、穏やかな時も、悲しい時も、楽しい時も、苦しい時も
いついかなる時でも私たちのことを見守っていてくれることを表している観音様です。
観音様の姿は立像が多いとされる中、能持院の観音様は座像であることが特徴的です。
またお姿は古来道場としての一面もあり、行に精進して到彼岸を迎え入れるお姿であるともいえます。

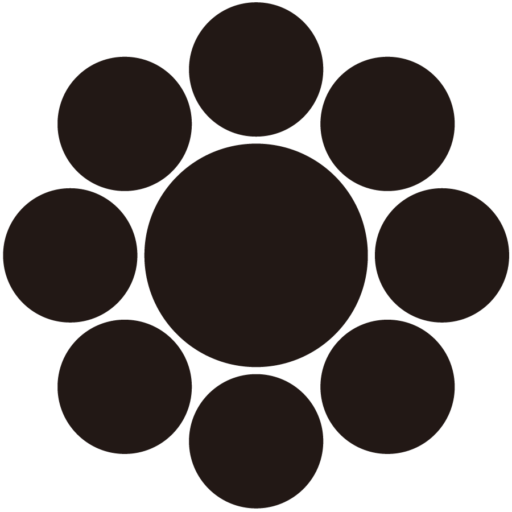
その他の主要建築物
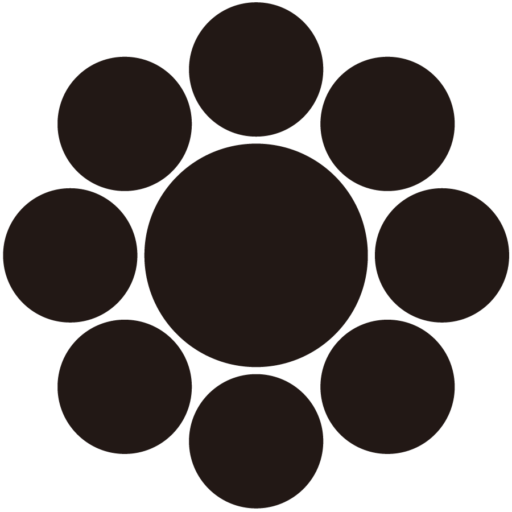
庫院(客殿)

木造平屋造銅板葺、間口十三間三奥行七間の建物。
昔は住職の住まい兼、弟子たちが過ごしていました。現在は客殿及び法要式場として使用されています。
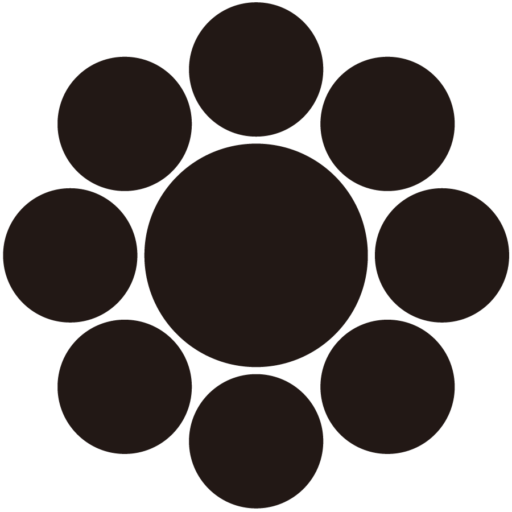
総門(山門)

木造単屋茅葺切妻造九尺四方袖塀付の建物。
山門は江戸時代の2回の火難に会うことなく、室町時代の建立されました。
かやぶき造りであり栃木県の重要文化財にも指定されています。
宮大工の左甚五郎が東照宮建立の際に能持院に寄り、山門の横梁に斧でくびれをつけたおかげで、外の火難が山門で止まったと言います。
また山内の火難が同じく山門の外に広がらないように念じたと言われており、それ以降は幸いにも火難にあうことはなくなったと言います。この逸話は「火伏の斧あと」と呼ばれており、能持院七不思議のひとつにも数えられています。
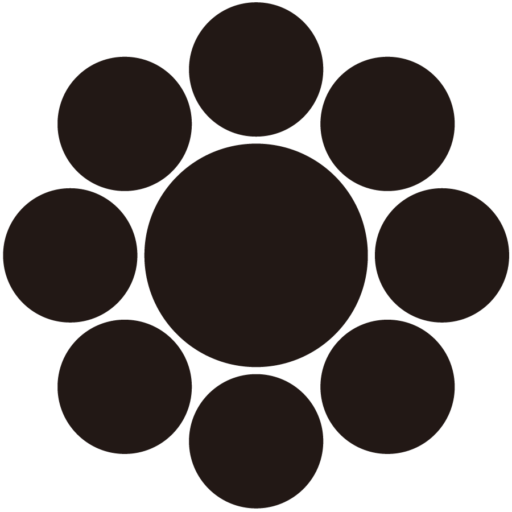
髙嶽堂

この能持院は、当院第二十三世機道髙傳大和尚代(一八〇五年)に火難にて山門を残して堂宇全焼。伽藍復興を果たすも第二十五世完月全光大和尚代(一八三五年)にまたしても山門を残し堂宇全焼の再難となってしまいました。
そこで茂木城主八代細川興建公の大発願により伽藍再復興に着手し、第二十七世髙嶽戒芳大和尚により堂宇伽藍落慶。その折に過去二回の火難を教訓とし、火伏の霊験あらたかな秋葉三尺坊大権現を勧請しその社である秋葉社を本堂東側に建立いたしました。
しかし台風倒木により社は倒壊し秋葉様御尊体は庫院内に遷座していましたが、平成二十五年に御尊体の修繕が完了し、翌二十六年七月七日秋葉三尺坊大権現の鎮守堂並びに秋葉様の御法力貴き浄火にてお焚き上げ供養が厳修できる道場として再度落慶いたしました。
その後秋葉様を勧請した第二十七世髙嶽戒芳大和尚の道号より髙嶽堂と命名し曹洞宗管長江川辰三紫雲臺猊下より扁額揮毫を賜りました。