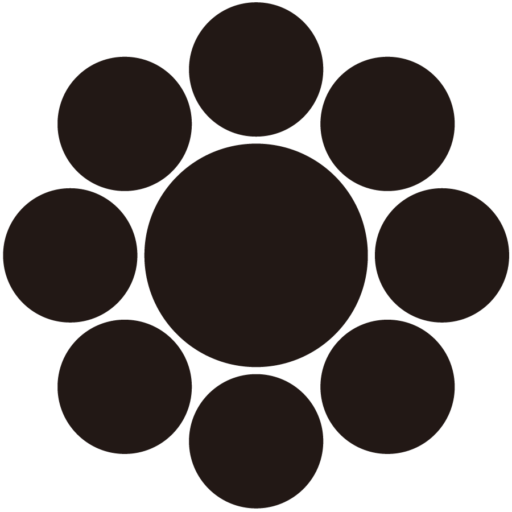
能持院が代々お守りしてきたお墓
茂木城主細川氏は初代興元から以後明治に至るまでこの寺を菩提所としました。
この墓所が通常の墓と異なる点は、墓石を設けずに墓標として1霊ごとに1本の杉を植え、
廟の前に没年月日を陰刻した石燈籠を設けていることです。
これは墓制史上、きわめて異例であり他に例を見ません。
老杉はありふれた墓石とは趣を異にして荘厳であり、いかにも禅寺の墓所にふさわしく細川家の威容をしのばせています。
墓所内には宝篋印塔1基と石燈籠13基が存し、いずれも没年銘があるので、
これが江戸時代における石造美術研究上きわめて貴重な資料といえるでしょう。
ぜひこのお墓を見るだけの目的で能持院へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

細川家と能持院の関わり
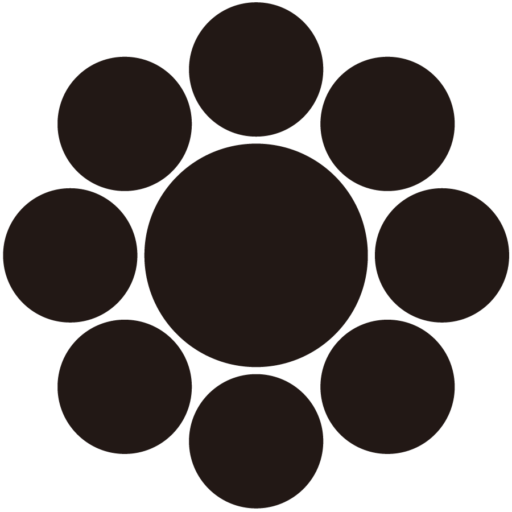
細川家ゆかりのお寺になった経緯

能持院は、この地で初めて茂木氏を名乗ったとされる茂木家の祖、八田知基(茂木知基)が1222年に創建した寺院です。
もともとは茂木氏の菩提寺でしたが、1610年に細川興元が茂木に封ぜられてからは、細川家代々の菩提寺となりました。
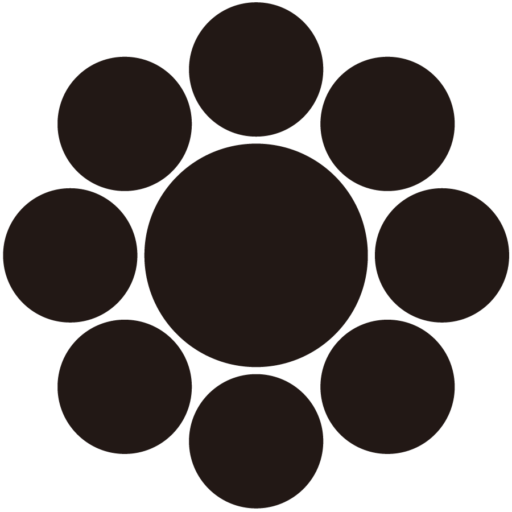
細川家と茂木の地

第一代目の細川興元は、戦国三英傑(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)に仕えるという、戦国時代の歴史を語る上では欠かせない存在です。
非常に重要な務めを果たした人物の一人で、徳川家第二代将軍秀忠から関ヶ原での勇猛果敢さを認められ、下野国芳賀郡茂木に一万石の領地を与えられて、その後茂木藩の初代藩主になったといいます。
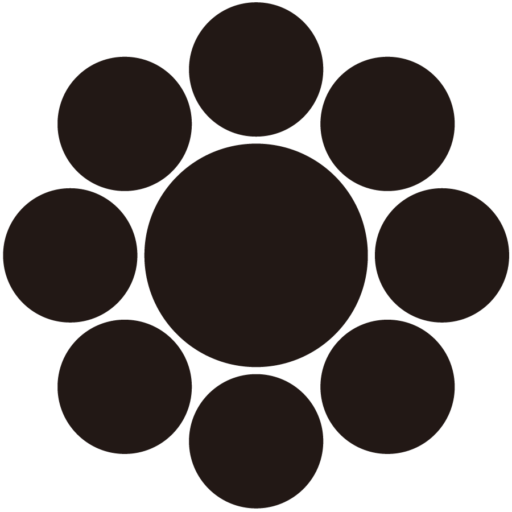
細川家代々のお墓

・324.7平方メートル
・墓標杉13本
・石灯籠13基
・昭和51年4月13日、栃木県指定史跡重要文化財となる。
現代における重要文化財としても非常に歴史深いことが特徴です。
墓所内には宝篋印塔1基と石燈籠13基が存し、いずれも没年銘が記されています。
第一代 興元
第二代 興昌
第三代 興隆
第四代 興栄
第五代 興虎
第六代 興晴
第七代 興徳
第八代 興建
第九代 興貫