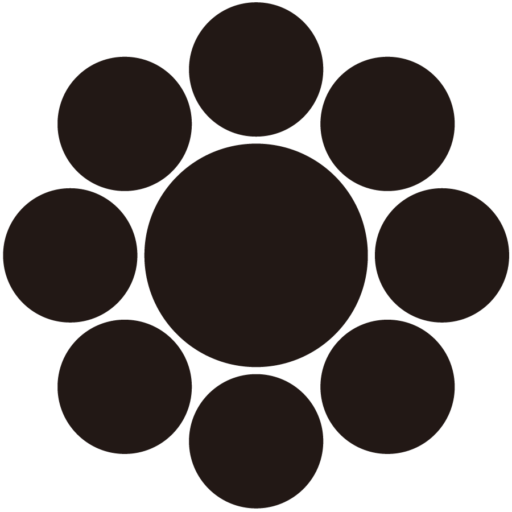
細川家が歩んできた時代

江戸時代を通じて、谷田部という地を領有した細川氏は、清和源氏の後えいで、室町時代に管領となっていた細川氏の一流に和泉守護家の細川元常がいた。
この元常には子供がなく、長岡(細川)藤孝を養子にした。藤孝は故事に通じており、織田信長や豊臣秀吉に仕え、晩年には徳川家康にも仕えた。藤孝の嫡子忠興は優れた戦国武将で熊本五十四万石を領し、細川氏の祖となった人である。次子の興元は生来きわめて乱暴者であったと伝えられている。
興元は朝鮮侵攻の時には兄忠興とともに参加し、続いて関ヶ原の戦いの時は徳川方につき忠興に属して出陣した。その後、徳川秀忠に召し出され慶長十五年(1610)七月二十七日、下野茂木一万石を与えられた。
大阪夏の陣の時興元は将軍秀忠の先隊として五番手の酒井雅楽頭忠世に所属して出陣した。元和元年(1615)五月七日、大阪城総攻撃の日、興元は酒井雅楽頭の嫡子阿波守忠行を補佐し、軍の指揮をとって奮闘した。
家康は興元の戦功を評して十万石の大名に引き立てようと兄忠興に伝えたところ、「弟は生来の暴れ者で十万石の器ではない。
彼を大名に取り立てることは、身を誤り国を乱すもとである。」と固辞した。
家康はこの言葉を受け入れ、興元には十万石の格式を与えたが僅かの加贈され、茂木と併せて一万六千石余りの大名となった。(関ヶ原の戦いの後、徳川氏に仕えた初代藩主細川興元は、大阪夏の陣の功績によって一万六千石余りを得て本城、茂木(現在の栃木県茂木町)の大名となった。)
そのあと、興元は兄が十万石を固辞した話を伝え聞き大いに立腹し、それ以後数百年にわたって熊本五十四万石の本家と不和になったと言われている。